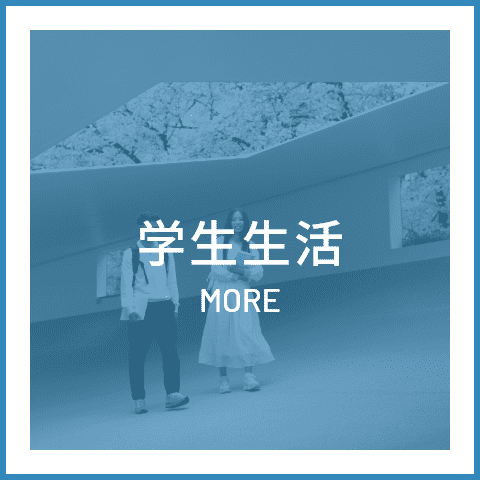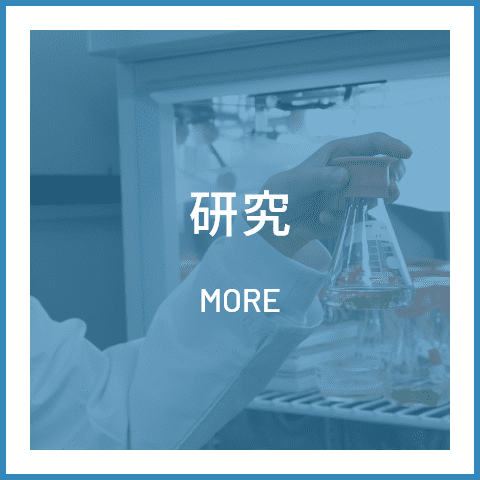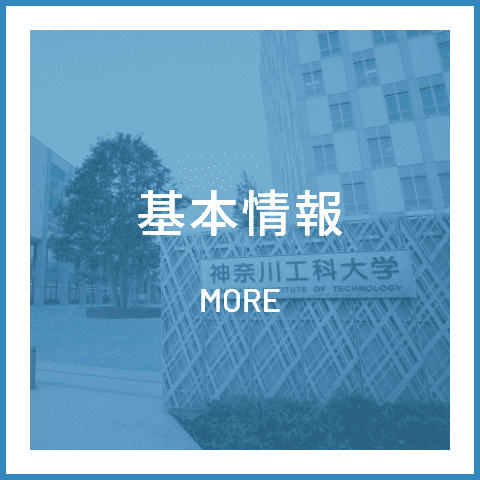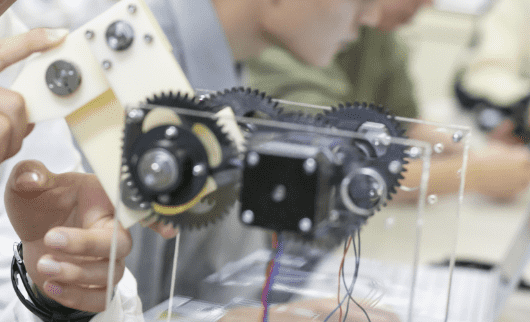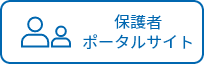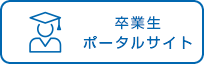フレイル予防からスポーツパフォーマンス向上まで~運動機能のデータ化と社会実装(先端工学研究センター 運動機能研究室 室長/基礎・教養教育センター 准教授 高嶋 渉)
スポーツの成績向上のためだけでなく、一般の人が自立・充実した日常生活をできるだけ長く続けるためにも、運動機能を高めたり維持したりする取り組みが非常に重要になってきています。運動機能研究室は、人間の運動機能とその要因についてさまざまな観点から数値化し、データを実社会でどのように役立てるかを大きな研究テーマとしています。

はじめに
「運動機能」のデータ化、と聞いて皆さんはどんな様子をイメージするでしょうか? 小学校から高校まで経験してきた新体力テストを思い浮かべる人が多いかもしれません。運動機能とは、「身体を動かす機能」のことであり、基本的には生まれてから青年期までは機能が向上していきますが、その後は老年期に向かって機能が低下しています。運動機能とその変化の様子は個人でも大きく異なります。高齢になってくると、筋力、柔軟性、俊敏性といった若者がイメージしやすいスポーツに関わる運動機能のみならず、骨、関節、認知機能や視覚・聴覚なども運動機能を構成する要因として機能低下していきます。
運動機能研究室のねらい
超高齢社会ではできるだけ多くの人が自分自身の運動機能の状態を具体的・客観的に把握し、健康寿命を伸ばすため、データに基づいた対策をとれる仕組みが求められています。スポーツ選手のパフォーマンス向上においても考え方としては全く同じです。運動機能研究室では、ヒトの各関節で発揮される筋力やパワー、実際に動作する時の床からの反力、重心の動きなど力学的な機能評価だけでなく、運動時に身体に取り込まれる酸素の量などの生理学的なデータも取得可能です。このような様々な運動機能に関するデータの観察と情報工学など他分野の技術を必要に応じて組み合わせることで、社会に貢献できる情報提供やシステムを開発することをねらいとしています。
研究・開発の例
運動機能低下がもたらす代表的な社会問題として「ロコモティブ・シンドローム」が挙げられます.運動機能研究室では,情報学部情報システム学科高橋勝美教授を中心に「筋力」、「歩行能力」および「認知機能」の運動機能データを安全・簡易に見える化する機器「健幸aiちゃん」を開発しました。さまざまな健康イベントや地域のフレイル(※)予防活動で高齢者の運動機能チェックを実施しています。「健幸aiちゃん」は、脚力を評価する「スタンドアップテスト」、歩行機能を推定する「3ステップテスト」、認知機能を評価する「カラーワードテスト」で構成されており、音声ガイドに従って測定することでスタッフの立ち合いを必要としないセルフチェックが可能なことも大きなポイントです。

今後の展望
近年、運動機能や身体活動の様子については、大学に設置されているような実験室で行う測定だけでなく、各種センサーを備えたウェアラブルデバイス等の普及によって日常生活や実際のスポーツ場面においても非常に有用なデータの取得、さらには対象者自身への頻繁なフィードバックが可能になってきています。運動機能研究室では、このような簡便でセルフチェック可能な運動機能評価や身体活動量評価を行うことが、日常生活行動や詳細な運動機能の評価データに及ぼす影響を明らかにし、健康寿命を伸ばすためのシステム実現や関連する問題の解決を目指していきます。
【用語解説】
※フレイル:年をとって体や心のはたらき、社会的なつながりが弱くなった状態
▼本件に関する問い合わせ先
研究推進機構 研究広報部門
E-mail:ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
▼関連するSDGs
3 すべての人に健康と福祉を